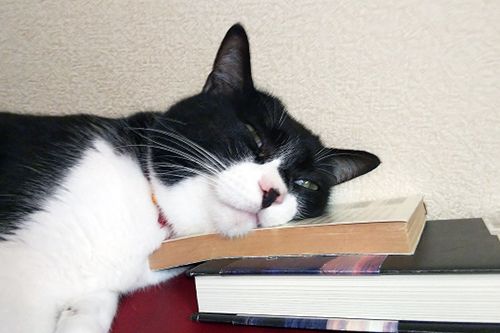動物看護師
公開日:最終更新日:
動物看護師が集まる動物病院の特徴とは?採用を成功させる5つのコツ【院長必読】

目次
はじめに|動物看護師の採用難、どう乗り越える?
全国的に慢性的な人手不足
2025年5月の有効求人倍率は1.24倍ですが、動物看護師の有効求人倍率は約1.68倍で、人手不足の傾向にあります。
有効求人倍率とは、求職者1人に対して企業がどれだけの求人を出しているかを示す指標です。
この数値が高いほど、就職しやすい「売り手市場」と言えます。求人に対して、求職者の方が多い状態を売り手市場と言い、求職者に有利な状況ということになります。
有効求人倍率が高いのにもかかわらず、人手不測になるのはなぜでしょうか?
離職率の高さと若手志向の変化
離職率に関する公式なデータはほぼありませんが、動物看護師の離職率は約30%、転職経験があるという回答は約40%となっています。
日本の平均的な離職率は2024年の統計では8.4%ですので、離職率の高さが非常に多いと言えるでしょう。
若手の代名詞のようになっているZ世代ですが、動物病院の経営者の世代とは仕事に対する考え方が異なります。
・「仕事のための人生」ではなく「人生の一部としての仕事」
・仕事に「社会的意義」を求める
・フラットな関係
などが、特徴と言われています。
そのため、
・意義や納得感が持てないと無理に耐えることなく辞める
・理不尽と感じる上下関係に我慢しない
・学べないと判断すると転職する
などの傾向があるようです。
採用力の差が病院経営に与える影響
先に紹介した背景だけが原因ではありませんが、飼い主さまやペットのよりよい医療を提供していくためには、病院にマッチした人材を採用する必要があります。
ミスマッチのない人材を採用し、しかも長く勤務してもらえる職場環境作りは、動物病院の内側の運営として非常に重要になります。
動物病院の運営をうまく続けていくには、外に向けた取り組み(お客様や地域との関係)と、院内の仕組み(スタッフの働きやすさや教育)を両方大事にすることが、院長や経営者にとって欠かせません。
まず知っておきたい|動物看護師の就職先の選び方とは?
若手層は「やりがい」だけでは動かない時代に
給与だけではなく「職場環境」「教育体制」「ライフワークバランス」を重視
「仕事とは何か?」という問いに対しての答えは、立場や環境によって多様な答えがあると思います。
・社会的役割
・収入を得る手段
・自己実現の場
・所属するコミュニティ
などが主なものと思いますが、どれを主にするのかは個人により異なるでしょう。若手層は給与も重視しますが、よく耳にするのは「生活できるだけの収入があればよい」という言葉です。もちろん、様々な考えの若手がいますので、給与に関して全く違う考えの方もいらっしゃると思います。
給与だけが良くても、働く環境や学びの場、プライベートとの両立が整っていなければ、働き続けたい職場とは思われにくい傾向があります。
SNSや口コミ、就活サイトの影響力も拡大
・オンライン化
会社説明会や面接が、これまでのように会社に行く形ではなく、自宅からオンラインで受けられるケースが増えています。
・ インターンシップが選考ルートに
気になる会社で短期・長期のインターンシップに参加し、そのまま就職につながる流れが一般的になってきました。
最近では、インターン参加者だけの特別な選考ルートを用意する会社も増え、インターンでの評価が内定に直結することもあります。
・ 口コミサイトでリアルな情報を確認
就職活動では、実際に働いている社員の声を口コミサイトで確認する人が増えています。
給与や退職理由、働き方など、以前は社員に直接聞いていたような情報が、サイトを通じて簡単に集められるようになっています。
・ 副業ができるかどうかも重要に
最近では、給与だけでなく、副業ができるかどうかを会社選びの条件にする若手も増えています。
自分のスキルアップややりがいを広げたいと考える人が多いからです。
個人病院と企業系動物病院の違いを理解する
教育・福利厚生・キャリアパス面での違い
| 個人病院 | 企業病院 | |
|---|---|---|
| 教育面 | 院長や先輩からのOJTが中心。マニュアル化されていないことが多い。 院長の考えや規模に依存するため、担当できる業務が限られることも。 |
入社時研修、社内マニュアル、eラーニングなど体系化されていることが多い。 組織が大きいため、専門分野(内科・外科・腫瘍など)の経験を積みやすい。 |
| 福利厚生 | 社会保険に加入している病院も多いが、小規模だと未整備の場合も。 シフトや残業代は院長次第。小規模だと人手不足で休みにくいことも。 産休・育休が実質的に取りにくい場合あり。人員の余裕がないと代替が難しい。 |
社会保険完備が原則。法定福利はほぼ100%整備。 シフト制度が整備され、有給取得率も比較的高い傾向。 産休育休制度の実績があり、復帰後の働き方も相談しやすい。 |
| キャリアパス | 看護師長、リーダーなどポジションは院長の意向次第。人数が少ないと役職が作れない場合も。 院内での異動は基本なし。転職する場合は自分で別の病院を探す。 看護師の独立開業は難しい。ただし院長に認められれば待遇アップの可能性も。 |
院内での役職(主任・マネージャー)や本部異動(教育担当、採用担当など)など多様な選択肢がある。 グループ病院内で異動できるので環境を変えやすい。 独立はしにくいが、会社内でのキャリアアップで役職手当や本部職に就く道がある。 |
採用戦略も「相手目線」で変える必要あり
先にも紹介したように、動物病院の採用は病院が求職者を選ぶ時代から、求職者が病院を選ぶ時代に変化してきています。特に動物看護師のような専門職は慢性的な人材不足で働きたい人が有利な立場になってきています。
・応募者目線
・働き手が感じる価値や魅力
・応募者が大切に考えているポイント
などを的確につかむ必要があります。
インターンシップや採用面接の際に、一方的な話だけでなく、「求職者の不安」「どのようなキャリアプランを描いているのか」「具体的な希望」などを会話の中から掴み取っていきましょう。
採用側と求職者の希望を擦り合わせ、お互いに一緒にやっていけそうかどうかを確認していくことも大切でしょう。
動物看護師が「働きたい」と思う病院の5つの条件
① 明確なキャリアステップと研修制度がある
自分がこれからどう進んでいけばいいのかは、なかなか一人では見えにくいものです。
だからこそ、動物看護師としてのスキルアップの道しるべがあれば、自分の将来の姿をイメージしやすくなります。
ただ「とにかく頑張ろう」と思っていても、途中でつまずいてしまうこともあるでしょう。
だからこそ、一歩一歩進めるように、歩くための“地図”を示してあげることが大切です。
② 人間関係が良好で、離職率が低い
人間関係の悩みは、どの職場でも多いと言われています。
動物病院も同じで、人間関係がうまくいかないと、どれだけ仕事が好きでも続けるのは大変です。
特に動物病院は「チーム医療」と呼ばれるほど、スタッフ同士の協力がとても大切です。意思疎通がうまくいかないと、医療ミスにつながる可能性もあります。
また、「指導」という名目でのハラスメントは、どんな理由があっても許されません。
人間関係を良くする取り組みとして、ペアシフトやクロストレーニングがあります。
例えば、ベテランスタッフと新人がペアになって一緒に働くと、分からないことをすぐに質問できたり、新人の成長や困りごとをチーム全体で把握できます。
さらに、部門を越えていろいろな仕事を経験するクロストレーニングを行うと、スタッフ同士がお互いの仕事の内容や大変さを理解できるようになります。
こうした仕組みがある病院では、自然と助け合う雰囲気が生まれ、業務の負担が一部に偏りにくくなり、スタッフが孤立しにくくなります。
③ 福利厚生や勤務時間への配慮がある
残業の有無、有休消化率、育休制度の実態など
以前は、動物病院では残業が当たり前のところが多くありましたが、最近は少しずつ減ってきています。
特に企業が運営する動物病院では、残業時間や休憩、有給休暇、育児休暇の取り方について、就業規則などでしっかりとルールが決められ、管理されています。
個人病院でも、福利厚生や勤務時間に配慮する病院が増えてきました。
法律に沿った働き方ができることも、「ここで働きたい」と思える病院の大切な条件のひとつです。
④ 病院の理念や方針に一貫性がある
「共感できるか」は採用可否の大きな分かれ目
多くの動物病院には、「理念」や「方針」があります。
これは「こんな動物病院にしたい」という経営者や院長の想いを形にしたものです。
この理念や方針に共感できないと、「一緒に頑張ろう」という気持ちが生まれにくく、長く働き続けるのが難しくなるかもしれません。
例えば、院長が「海を目指そう」としているのに、自分は「山に行きたい」と思っていると、進む方向が合わず、病院もうまく回りません。
同じ方向を向いて力を合わせていけるかどうかは、働く上でとても大切なポイントです。
⑤ 面接や見学時の対応が丁寧
病院見学や面接のときに、求職者に残念な思いをさせていないでしょうか?
例えば、院長がほとんど話をしなかったり、診療が忙しくて求職者をほとんど放置してしまうのは、よくある残念な対応の一つです。
求職者は数ある動物病院の中から、自分の時間を使って見学や面接に来てくれています。
その気持ちを大切にして、しっかり向き合って対応することが大切です。
「病院が人を選ぶ」だけでなく、求職者も病院をしっかり見ています。
求人原稿で差がつく!動物看護師採用のポイント
伝えるべきは「待遇」より「理念・職場の魅力」
募集要項のテンプレではなく、自院らしさが伝わる文章に
私たち自身が仕事を探すとき、どんなことを知りたいでしょうか?
多くの人は、
・給与やボーナス、福利厚生、退職金、学会・書籍の補助などの待遇面
・職場の雰囲気や人間関係
・病院の理念に共感できるかどうか
といったポイントを気にすると思います。
でも、これらは知りたい情報であると同時に、不安を感じやすい部分でもあります。
どれだけ雇用条件が良くても、不安が残る職場にはなかなか応募しにくいものです。
ちなみに筆者自身の例では、「参加しなければならないイベントが多い病院」は、どんなに条件が良くても選べませんでした。
求職者は「何が知りたいか」と同時に「何が不安か」にも目を向けています。
写真と動画の活用で職場のリアルを見せる
病院の一日の流れがあらかじめ分かっていると、見学や面接に来る人にとって大きな安心につながります。
どこから入って、誰に声をかけて、どのように一日を過ごすのかがわからないと、不安や緊張が大きくなり、せっかく興味を持ってもらっていても気持ちのハードルが上がってしまいます。
実際の病院での一日のスケジュールや、スタッフがどのように働いているかを紹介するだけでも、求職者にとっては「自分が働く姿」をイメージしやすくなります。
さらに、文章だけでなく、仕事風景を映した動画やスタッフのインタビューなどがあれば、職場の雰囲気がリアルに伝わり、親しみやすさがぐっと高まります。
事前に病院の様子が分かることで、「この病院で働いてみたい」と思うきっかけになり、見学に来る際の不安も大きく減らせます。
求職者に安心して病院を訪問してもらうために、1日の流れや職場のリアルな様子をわかりやすく発信することは、とても大切なポイントです。
採用後の定着を左右する“働きやすさ”の整備
オンボーディング(初期教育)の仕組みが鍵
「何も教えてもらえなかった」という声が、退職理由としてよく挙がるのを耳にします。
特に新卒スタッフが多く入社する4月は、動物病院も忙しくなり、教育の時間を取りにくい時期です。
だからこそ、新しく入ったスタッフが安心して仕事を始められるように、初期教育の仕組みをしっかり整えておくことがとても大切です。
基本的な業務の流れや病院の方針、先輩スタッフとの関わり方などを、段階的に学べるプログラムを用意することで、新人は早く職場に馴染み、自信を持って仕事ができるようになります。
一人ひとりの習熟度に合わせて進められるオンボーディング(初期教育)こそが、スタッフの定着と成長を支える大切な土台です。
また、教える担当者によって教え方や内容に差が出ないように、教える側の教育や情報共有もとても重要です。
定期面談と評価制度で、成長と不安のフォローを
スタッフ一人ひとりが安心して力を発揮できるように、定期的な面談と分かりやすい評価制度を整えましょう。
面談では、仕事の進み具合だけでなく、困っていることや将来の目標まで一緒に話し合い、必要なサポートを考えます。
評価では成果だけを見て終わりにせず、日々の努力や成長の過程もしっかりと認める仕組みにすることが大切です。
そうすることで、不安をため込まずに次のステップへ進める、安心できる職場をつくることができます。
まとめ|「選ばれる病院」になるために、今できること
採用は競争ではなく、働く人に「ここで働きたい」と選ばれるための準備です。
院内の環境づくり、教育体制、情報発信を見直すだけでも、大きな変化につながります。
もし「応募が来ない」「定着しない」と感じたら、まずは自院の働きやすさや伝え方を見つめ直すことから始めてみましょう。