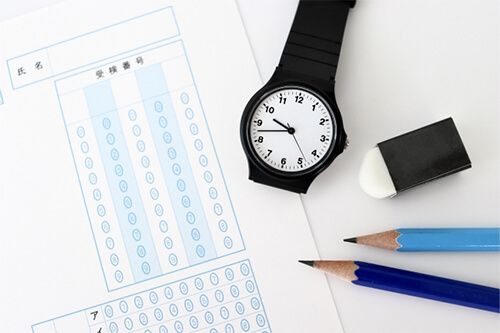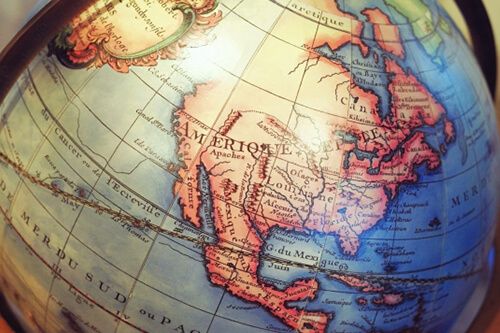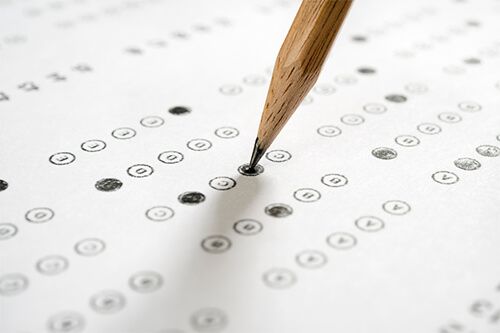獣医師の情報発信
公開日:最終更新日:
【2026年最新版】獣医師の海外キャリア|留学・転職のリアルとその準備とは?

いつか海外で獣医師として働いてみたい―そんな想いを抱いたことはありませんか?
英語や資格、資金などの壁に不安を感じる人も多いですが、実は海外でキャリアを築く道は誰にでも開かれています。
この記事では、獣医師の留学や海外転職のリアル、そしてその第一歩を踏み出すためのヒントを紹介します。
目次
獣医師の海外転職・留学のススメ|世界で活躍する選択肢
日本のパスポート取得率がたった17%というニュースを見た方もいるのではないでしょうか。
ここ数年日本から海外に羽ばたく留学生の割合が少なくなっている、という話を聞くことがあります。実際COVID-19の影響や、最近の世界情勢が足踏みをさせてしまうのは理解することができます。
しかし、獣医療業界でみてみると、個人的な印象ですがひと昔よりも海外に目を向ける獣医師が多くなった印象を受けます。
「専門医」というものが欧米だけではなく日本国内でも設立されたり、医療の発展などがより拍車をかけているのかもしれません。
しかし、やはり留学や海外転職は多くの獣医師にとって大きなハードルであることは確かです。
「英語」という言語の壁の高さはもちろんのこと、ビザの問題やお金の問題、治安や将来性の問題など、踏み出す一歩を躊躇してしまうのも頷けます。
また海外にいけるのはいろんな面で恵まれている「エリート」という印象があるのも確かです。
しかし、チャンスはどこにでも転がっています。そして誰にでも平等にあります。
ここでは獣医師の海外転職や留学のメリットや課題、準備の流れなどを解説していきます。
ただしあくまで一つの意見だということと、昨今の世界情勢の動きによって左右されてしまうこともあるため、必ずしっかりご自身でも調べる必要があることを忘れないようにしてください。
なぜ今、獣医師に「海外」が注目されているのか?
昔から「国際学会」はもちろん開かれていましたし、実際に参加されている先生も多くいらっしゃいました。
しかし、医療の発展とともに、より高度な知識や技術が獣医師にも必要になってきているのは確かです。
実際に昔は「獣医師が患者を選ぶ」と言われていましたが、今は「患者が獣医師を選ぶ」という時代になっています。
また就職先を選択する際も、ただ近所だから、という理由だけではなく、「専門」を持っている先生のもとで学びたい、しっかりとした施設で働きたい、など意識が高い獣医師が増えたことも、海外を目指す獣医師が増えた理由になっているのではないかと個人的には思っています。
さらに動物の高齢化がすすみ、様々な病気がみられるようになったことで、より情報を得るためにはどうしても日本だけではなく、世界に目を向ける必要があります。
これも一つの要因となっているのではないでしょうか。
留学 or 海外転職?|目的別に異なる「海外キャリアの形」
海外でキャリアを形成するためにはいくつか方法があります。
大学・研究機関での留学
一つは大学や研究機関へ留学する方法です。
これはいわゆる「大学院進学」もしくは「ポスドク」という立場で所属するパターンになります。
基本的には臨床というよりは研究がメインとなってきますので、研究者としてのキャリアを積みたいと考える獣医師にはとてもいい機会となると思います。
大学院に進学して博士号を取得する場合は基本的に「学生ビザ」というものが必要になってきます。
比較的取得しやすいビザではありますが、今年アメリカで「学生ビザ」の発給を停止し、取得のための必須のプロセスである大使館での面接がストップしてしまうということがありました。
現在は特に問題ないようですが、世界情勢に左右されてしまう可能性が今後もあるかもしれません。
また金銭面でも大学院進学なので入学金をはじめ大学に支払う費用が必要になります。
ただ色々な奨学金がありますので、うまく活用してみるといいかもしれません。
筆者も今になってこんなにも使える奨学金があることを知り、もっと前にしっていればと少し後悔しております。
もう一つは「ポスドク」という立場で受け入れてもらうという方法です。
この場合は「J₋1ビザ」と呼ばれるものが発給されることが多いと思います。
ポスドクとは研究プロジェクトを手伝う研究者のことで、期限が決まっています。
期限はプロジェクトや所属する機関によるとは思いますが、J1ビザは最長5年という決まりが設けられていますので、メリットの一つとしてはずっと働くことができないという点があげられます。
また、お金をもらうという行為ができないので、無給の場合もあり実費ですべてをまかなわなければならない場合もあります。
もちろんプロジェクトや機関によってはお給料を研究費から支払ってくれるところもありますので、確認が必要になってきます。
臨床目的の海外実習・インターン
獣医師が海外で働く方法としては、インターンやレジデントになることも一つの選択肢として入ってきます。
この場合ハードルはとても高くなります。
なぜなら、基本的には年に1度実施されるマッチングプログラムに応募しマッチしなければならないからです。
マッチングプログラムとは、大学側が欲しい人材を募集して応募者がその条件に合えば、インターンやレジデントとして大学が定める期間、研修プログラムを受けることができるものです。
これは外国人に対して行っているものではなく、ネイティブも含めたものですので必然的に門戸はとても狭くなります。
言語の壁はもちろんビザの問題など簡単に入れるものではありません。
インターンは基本1年のプログラムで就労ビザでのことが多く、レジデントは基本的に3年のプログラムで学生ビザや就労ビザのどちらかである場合がほとんどです。
レジデントは3年間のプログラムを修了すると専門医の試験を受ける資格が与えられ、無事試験に受かると「Specialist」として名乗ることができます。
他の方法としては、大手の動物病院などが独自の研修を行っている場合もあり、稀ではありますが短期間で私たち日本人を受け入れてくれる所もあるようです。
あとは特殊な方法ではありますが、自分自身で気になる動物病院や先生にコンタクトをとり、相談してみるという手もあります。
返事が返ってこないことも多くあるので、もし本当にどうにか海外での道を見つけたい人はトライしてみてもいいかもしれません。
海外での道をみつけるためには待っているだけではチャンスは絶対やってきません。
それぐらいの行動力は必要かもしれませんね。
製薬企業・NGO・外資系動物医療企業への転職
獣医師が海外で働くその他の方法としては、製薬会社なども含めた外資系企業への就職というのもあげられます。
ただこれはとても稀だと思います。
多くの獣医師は外資系企業に就職しても、出張など短期間のチャンスはあるかもしれませんが、実際にアメリカやヨーロッパなどの支社や本社で務められる機会は少ないと思われます。
ある程度学位を持っている(博士号など)場合は、もしかしたら研究員などの立ち位置で希望すればチャンスはあるかもしれません。
が、全員に平等にあるものではないと思います。
実際に挑戦するために必要な準備
① 英語力(TOEFL/IELTS/職務上の実務英語)
もちろん、実際に海外に挑戦する、となった場合、語学力は必須です。
もちろんどこの国にいくかによって多少変わって来ると思いますが、ここでは一番需要が高い英語についてお話していきます(アメリカの場合についてお話していきます)。
いくら「臨床ではないから」「研究職だから」といっても英語でのコミュニケーションができなくては生活していくことも難しいですよね。
もちろん、どこを目指すかによって必要な英語力は違ってきます。
例えば、学生ビザを発行してもらう場合、つまり学生としてアメリカに行く場合(大学院留学やレジデント)は、
- IELTS: 6.5~
- TOEFL: 80~
が多くの場合要求されると思います。
もちろん大学ごとに基準が違っているので、必ず自分で確認する必要があります。
大学によってはもっと高いスコアが必要なところもあります。
また就労ビザを発行してもらう場合、多くは英語のスコアは要求されないことが多い印象です。
ただし、実際に外国で働いて生きていくには、何度もいいますがコミュニケーションがとれる英語力はマストです。
英語のテストを受けなくていいからといって、”楽”なわけではまったくありません。
ポスドクなど期限つきでの受け入れであっても、多くの大学は英語のスコアの提出を必須にしているところが多いと思います。
もちろん、臨床や大学院留学などよりは必要なスコアは低いですし、TOEFLやIELTなどの難しいテストだけではなく、「Duolingo」など最近新しくできた比較的簡単な英語の試験でも受け入れてくれるところもあります。
外資系企業の場合は、就職時にTOEICが必須になっているところも多くあるかと思います。
ただ気を付けてほしいのは、TOEICは日本での英語力をみるテストであって、海外の大学や研究機関では英語のテストにTOEICは含まれておらず、使うことができません。
ですので、「TOEICの点数が900点あるから大丈夫!」と勘違いしないように注意が必要です。
② 現地の資格・免許事情
日本の獣医師免許は日本だけのもので海外では認められていません。
なので、例え日本で獣医師をしていたとしても、海外では獣医師として働くことは基本的には認められていません。
筆者のいる北米では、獣医師の資格を取得する方法は大きくわけて2つあります。
- ①北米の獣医大学に入る
- ②テストをうける
北米には日本でいう国家試験があります。
これは「NAVLE(North American Veterinary Licensing Examination)」というものです。
これに合格することで、北米で獣医師として働くことができます。
これを受験するためには、北米の獣医大学(アメリカの獣医師会が認めている大学)を卒業することが必要になってきます。
しかし、もちろん日本人の獣医師がこの方法を選択する場合、金銭面はもちろんのこと獣医大学に入学するにはハードルが高いので、とても難しい方法でもあります。
もう一つの方法も決して楽な道ではありません。
これは大学に入りなおす必要はないですが、ECFVG(Education Commission for Foreign Veterinary Graduates)というプログラムを修了する必要があります。
これも、簡単な道ではありません。
このプロセスのなかにはTOEFLなどの英語のテストなども含まれます。
要求されるスコアも大学院などに入学する場合に必要なスコアよりもより高い点数ですので、どちらにしろ努力が必要になってくるのは確かです。
そして、このプログラムを修了してはじめて国家試験を受ける資格を得られます。
どちらの方法も時間とお金、そして根気と努力が必要になってくるのは明白だと思います。
そしてNAVLEに合格後は州によっても定める免許の制度が違うため、それぞれの州法にのっとった手続きが必要になります。
ここまで行ってやっと獣医師として働くことができます。
英国は北米と違い、EAEVE(欧州獣医学教育機関協会)の認定校を卒業することで獣医師国家資格の受験資格を得ることができます。
日本でもいくつかEAEVE承認を受けている大学があるため、そちらの大学を卒業して獣医師免許を取得していれば、イギリスの獣医師国家資格を受験する必要はありません(もちろん手続きは必要ですし英語のスコアは必要です)。
しかし日本のすべての学校がEAEVEの認証をうけているわけではないので、認証をうけていない獣医師がイギリスで国家資格を取得するためには、英国王立獣医師会(RCVS)の認定をうけなければいけませんが、これにも英語のテスト(IELTS)の高いスコアだけでなく、高い英語力が要求されます。
③ 資金計画(学費・渡航費・生活費)
海外に飛び立つ場合、英語だけが問題ではありません。やはりお金は必要になってきます。
今はいろんな留学奨学金があります。
ほとんどは大学院を含めた学生を対象にしたものですが、中には研究者向けのもの、大人向けのものもあります。
もちろん、返済不要のものも多くありますので、気になる方はぜひ調べてみるといいかもしれません。
「トビタテ!留学JAPAN」などは有名な奨学金の一つです。
今円安が進んでおりますので、資金もそれなりにかかります。
生活費をとっても家賃が場所によりますが日本円でも15万ほどからが多いと思いますし、物価の高騰はアメリカでも起こっていますので、日本で同じように生活するよりも高くつくことは間違いありません。
また大学院など学校への留学の場合、インターナショナルの学生に対してアメリカ人よりも高い学費を設定している大学が多いです。
もちろん、インターンやレジデント、もしくは研究者(一部)として働く場合はお給料をもらいながら生活することができます。
ただし、ビザの問題がアメリカは昨今より厳しさをましていますので、注意が必要です。
ビザの種類によっては収入を禁止されているものや制限があるものがありますので、必ず自分自身で確認するようにしましょう。
実際に海外に挑戦した獣医師のリアルな声(エピソード紹介)
筆者はアメリカに渡米して1年が経ちました。
私は博士号を持っているので、「ポスドク」という肩書で「J1ビザ」でアメリカに滞在しています。
J1ビザでは働くことができないので、資金面の工面がとても大変で、今もですが家族に支えられて生活しています。
また、英語はもともと小さい時から習っており、慣れ親しんでいたので嫌いという感覚はなかったのですが、やはり実際にアメリカで暮らすというのはとても最初大変でした。
性格がお恥ずかしながらとても適当で「まあいいや」精神の私でも、気分が落ち込みしんどい日々がありました。
もちろん言語の壁はあります。
でもそれがすべてではないと感じます。
言語はツールなので、「英語が話せないこと」は解決方法があるのでどうにかなります。
しゃべらざるおえないし、勉強しなければならないので、正直私にとってはそちらよりも、精神的な部分が大きかったように思います。
日本では獣医師として働けてキャリアもあったのに、こちらではアメリカの獣医師の資格がないので医療行為はできないですし、「何者」でもない、というのがとてもしんどかったのを今でも覚えています。
そして日本では感じなかった、自分が「マイノリティー」であることがさらに自分を追い込んでいたと思います。
アメリカはいい意味でも悪い意味でも多様性の国です。
誰も他の人がどんな人であろうと気にかけません。
それはいいところでもあるのですが、日本人である私からすると、なんでも気にかけて配慮してくれる日本文化と比べるととても冷たく感じてしまったのも事実です。
今は開き直り、そしてずうずうしくなったので、自分が「日本人」であることを受け入れ誇りに思っていますし、ネイティブになろうとするのも、英語をうまく話そうとするのもやめた(諦めた、がただしいかもしれません)ので、まったく落ち込むこともないですが、1年で強くなったな、と感じます。
また友達もできて、自分のコミュニティーも広がったのも大きいのかもしれません。
私は恵まれているので、助けてくれる人がいっぱいいます。
でも助けてくれるのを待っているのは違います。
「助けて」と声にだせる勇気や強さも必要だと1年たった今しみじみ思っています。
海外キャリアを視野に入れる若手獣医師へのアドバイス
コロナという大きな出来事が世界中の距離を縮めたのは確かで、今では気軽にどこにいようとも、パソコンさえあれば仕事ができますし、勉強もすることができるようになりました。
それは色んな人にチャンスがあるということです。
今ではオンラインから参加できる国際学会や、プログラムもありますし、世界中の論文や講義を日本にいながらオンラインで読んだり聞くこともできます。
海外に飛び出すには勇気がいりますし、とても大きな決断だとおもいますので、まずは、”日本にいながら”海外を感じられるものから始めてもいいのではないでしょうか。
英語の勉強にもなりますし、自分のモチベーションにもなると思います。
さらには、Social mediaが昨今急激にのびてきています。
色んな問題もありますが、やはり色んな人とつながれる、そしていろんな情報を得られるというメリットが大きいかと思います。
これを利用しない手はないと思います。
海外に出た先輩方とつながって(獣医の世界は狭いのでどこかでつながれます)コネクションを作ったり、アドバイスや情報をもらって、自分がどうしたいのか考えることもできます。
いい意味で「使えるものは使う」ということは大切です。
そして覚えていてほしいな、と思うのが、やはり人とのつながりです。
一人でもできるかもしれませんが、人の助けがあってこそなりたつものだと思っています。特に海外に行くというのは人の助けが大きく関わってくると個人的には思っています。
ただ、人の助けを得るためには、自分が行動することが前提となっているのも忘れてはいけません。
そしてその行動は最初は大きくなくてもいいのではないかと思います。
海外に行きたいな、と思っているだけではいけません。
それを誰かに言うという行動が、次につながる一歩になります。
思うだけでなく、そうやって小さなことから、そして自分のできる範囲のことから始めてみてください。
まとめ|海外での経験が、獣医師としての視野を変える
何度もいいますが、大事なのは「行動すること」「人とのつながり」です。
この二つが個人的には大事だと思っています。
日本の素晴らしい文化である、空気を読んで手を差し伸べたり、何かをやってあげる、という文化や考えは海外にはありません。
そしてそれが「いいこと」という認識もありません。
待っているだけではチャンスは絶対に来ません。
ですので小さなことからでもいいので行動してみてください。
それは、思いを口に出して人に伝えてみる、でもいいですし、気になる先輩獣医師に連絡をしてみる、というものでもいいと思います。
その人に見合った範囲の中で、無理せずに動いてみてください。
そして絶対に他人と比べないでください。
うらやましく思うこともあると思いますし、出来ないことに悔しい思いをすることもあるかもしれませんが、人それぞれタイミングがありますし、持っているものも違います。
なので他人に目を向けるのではなく、自分自身に目を向けてぜひ夢をかなえましょう!